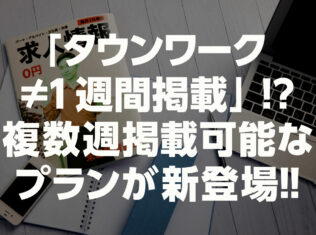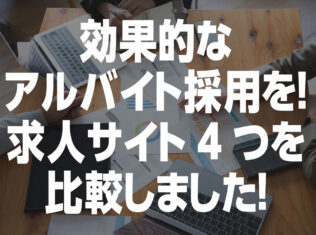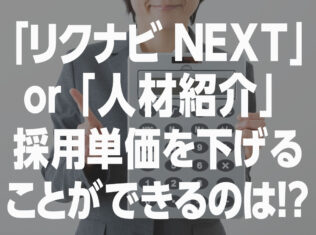目次
「同じ仕事には同じ賃金を」――同一労働同一賃金の考え方とは?
同一労働同一賃金は、非正規雇用(パート・契約社員・派遣社員など)と正社員との間にある不合理な待遇差を是正するための制度であり、働き方改革の柱のひとつとして位置づけられています。
同じ職務内容・責任・配置転換の範囲で働く労働者には、雇用形態にかかわらず「同じ賃金・待遇」が支払われるべきという考え方です。
企業側に求められる対応
- 評価制度の見直し
- 賃金体系(基本給・手当・賞与など)の整備
- 福利厚生・教育訓練における差の合理性の検証
これらの取り組みは一見、手間やコストがかかるように感じられるかもしれませんが、従業員の納得感やモチベーションの向上につながり、ひいては企業全体の生産性向上にも寄与します。
制度導入のステップ
- 現状の雇用区分ごとの待遇・賃金の「見える化」
- 業務内容・責任・配置転換範囲の整理
- 待遇差の合理性についての検証
- 是正方針の策定と従業員への説明
- 制度改定と運用・継続的な見直し
同一労働同一賃金の遵守は、2020年から順次施行されており、中小企業にも適用されています。違反があった場合には損害賠償請求が発生する可能性もあるため、制度の理解と対応は急務です。
実際の事例と対策
たとえばある企業では、契約社員に対して「通勤手当」や「住宅手当」が支給されていなかったことが問題となり、裁判で不合理と判断されたケースがあります。こうしたケースを防ぐには、待遇差の「合理的な説明」ができる基準とドキュメント整備が欠かせません。
・働き方改革関連法
・均等待遇・均衡待遇
・労使協定
・無期転換ルール
・パートタイム・有期雇用労働法
就職氷河期世代とは?|採用のポイントや人材活用ノウハウから注意点
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金の基本概念
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用労働者(パート・契約社員・派遣社員など)において、業務内容・責任・配置転換の範囲が同等である場合には、賃金や待遇を同等にすべきという考え方です。
昨今では非正規雇用の増加により、正社員との間で待遇格差が顕在化。これにより労働者のモチベーション低下・離職・人材流出などの課題が浮き彫りとなり、社会全体の労働環境の健全化を目指す必要性が高まっています。
規定されている法律とその背景
2020年施行の「パートタイム・有期雇用労働法」改正により、同一労働同一賃金はすべての企業にとって義務化されました。
この法改正の背景には、非正規雇用者の待遇差拡大とそれによる不満・早期離職といった社会問題が存在します。
現在では、企業が待遇差の合理性について説明責任を果たすことが求められており、説明できない格差には是正義務が発生します。
同一労働同一賃金ガイドラインの概要
厚生労働省が策定した「同一労働同一賃金ガイドライン」では、以下のような待遇項目ごとに不合理な格差がないかを判断する基準が明記されています。
- 基本給(職能・職務・業績連動などの評価基準)
- 賞与(支給対象・算定方法の明確化)
- 各種手当(通勤手当、家族手当、住宅手当など)
- 福利厚生(休暇制度、社内施設、健康診断など)
- 教育訓練(研修機会、スキルアップ支援など)
企業はこのガイドラインを基に、自社の評価制度・賃金体系の透明化と再設計を進める必要があります。対応を怠ると、労働者からの訴訟リスクや企業イメージの悪化にもつながりかねません。
・パートタイム・有期雇用労働法
・均等待遇・均衡待遇
・働き方改革関連法案
・非正規雇用是正
・労働者派遣法の適用範囲
・人事評価制度・賃金制度の見直し
同一労働同一賃金のメリットと課題
従業員のモチベーション向上
待遇差の是正により、非正規雇用者のやる気・責任感が向上します。
「どうせ評価されない」といった不満が軽減され、正社員と同様のキャリア形成意識が芽生えやすくなります。
人材スキルの向上と企業の発展
待遇見直しにより、非正規雇用者の定着率が向上し、長期的なスキル蓄積が可能になります。
これにより、育成投資の効率化とともに、内部人材の活用という好循環が生まれます。
- 報酬が職務内容に即して設計される
- 専門性を重視した人材戦略が構築できる
- ジョブ型雇用への移行にも対応しやすい
企業イメージの向上
公平な待遇は、求職者や既存社員からの信頼を得るために不可欠です。
同一労働同一賃金を推進する企業は、以下のようなプラス効果が期待できます。
- 「働きやすい会社」としての評判向上
- 採用力の強化(特に若手・女性層への訴求)
- SDGs・ダイバーシティ経営への対応
注意すべき課題(人件費増加、人事制度の見直し)
一方で、待遇の平準化には以下のような課題も存在します。
- 人件費の増加リスク(特に短期的に)
- 等級制度・評価制度の再構築の必要性
- 社内調整や説明責任の負担
- 逆に不公平感が生じないよう配慮が必要
経営層・人事部門の連携と、従業員への丁寧な説明が成功のカギとなります。
合理的な待遇差が認められるケース
同一労働同一賃金とは、すべての待遇差を無くすものではありません。
以下のような合理的な違いがある場合には差を設けることが可能です。
- 職務内容や責任のレベルが異なる
- 転勤や異動の有無
- 勤務年数や能力の違い
厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、これらの判断基準が明示されています。企業はガイドラインを参照し、制度設計と運用の整合性を保つ必要があります。
・非正規雇用のモチベーション管理
・ダイバーシティ経営
・ジョブ型人事制度
・人件費マネジメント
・SDGsと雇用の質の向上
働き方改革の実践事例
中小企業における成功例
中小企業においても、同一労働同一賃金の導入により待遇改善や人材定着に成功する事例が増加中です。
特に現場業務などで職務が明確な職種では、職務評価制度や等級制度の導入によって正社員・非正規社員間の不公平感が軽減され、結果として定着率や生産性の向上につながっています。
以下に、評価制度の透明化・処遇の公平性・多様な働き方への対応という観点で、実際に成果を上げている中小企業・法人の事例をご紹介します。
🔹 パートタイム従業員の待遇改善と評価制度(株式会社アル・マイーム)
等級制度をパート従業員に適用し、業務スキル・貢献度に応じた昇給制度を整備。
勤務年数だけではなく実績や姿勢で評価される仕組みを構築したことで、長期的な雇用意欲と働きがいが向上。
🔹 職務評価による公正な処遇(社会福祉法人郡山コスモス会)
全職員に対して「職務評価表」を導入し、業務内容や責任を点数化。
点数に基づいて手当や昇給を設定することで、正規・非正規を問わない公正な評価制度を実現。
職員間の信頼関係を深め、組織文化の安定にも寄与。
🔹 障害者の多様な働き方への対応(NPO法人福岡県障害者雇用支援センターあゆむ)
障害を持つ労働者にも能力に応じた給与体系を導入。
業務の標準化や補助システムの整備により、個人の強みを発揮できる環境を提供。
多様性の尊重とダイバーシティ経営を実現する好例。
🔹 従業員の意欲向上と評価制度の透明化(株式会社小金澤商店)
職務評価制度を見直し、「誰が・何を・どこまで」を明確に。
目標設定がしやすくなったことで、モチベーションが向上。
非正規社員にも昇給・表彰の機会が用意され、公平性とやる気を両立。
🔹 労務管理の改善と規則見直しの効果(株式会社三基)
労務管理システムを刷新し、正社員と非正規社員の労働条件を明文化。
就業規則の見直しにより業務内容・労働時間が明確化され、従業員の不安や誤解を解消。
結果として離職率の低下と採用コストの抑制にも成功。
・職務評価制度の導入事例
・等級制度と非正規雇用
・中小企業の人事制度改革
・離職率の低下施策
・ダイバーシティ・インクルージョン推進
具体的な取り組みポイント
🔹 職務内容や責任の明確化
正規・非正規問わず、職務の内容と責任範囲を明確に定義することが、同一労働同一賃金の第一歩です。
曖昧な職務記述は、不満や誤解・トラブルの原因となりやすいため、職務記述書(ジョブディスクリプション)の整備が重要です。
🔹 処遇透明性の確保と信頼関係の構築
評価基準や昇給ルールの公開は、従業員との信頼関係を築くうえで不可欠です。
処遇決定のプロセスに透明性を持たせることで、不公平感を防止し、組織へのエンゲージメント向上につながります。
- 評価制度の整備と見える化
- フィードバック面談の定期実施
- 昇給・賞与ルールの文書化と共有
🔹 正社員と非正規雇用労働者の待遇差検証
「パートタイム・有期雇用労働法」により、企業は待遇差の合理性を検証する義務を負っています。
福利厚生や教育訓練などの項目についても、職務内容・責任・就労実態と照らし合わせて差を分析する必要があります。
🔹 労働条件の見直しと待遇の向上
待遇改善は賃金面だけではなく、福利厚生・教育制度・キャリア支援など多方面からのアプローチが必要です。
特に、非正規雇用者への教育訓練の機会提供やキャリアパスの明示は、長期雇用へのモチベーションを高め、企業の成長にも直結します。
- 非正規社員向け研修メニューの整備
- キャリア面談の実施と昇格制度の導入
- 福利厚生の一部共通化(休暇制度・社内施設など)
・職務記述書(ジョブディスクリプション)
・評価制度の透明性
・待遇差の合理性と説明責任
・キャリアパスの整備と人材育成
・非正規雇用者のモチベーション向上
同一労働同一賃金を支える法制度と支援
働き方改革を推進するための法律
働き方改革関連法の中でも、特に重要なのが
「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働契約法」です。
これらの法律は、正社員と非正規雇用者の不合理な待遇差を禁止し、企業に対して合理性の説明責任を課す法的枠組みを提供しています。
また、以下のような制度的取り組みも求められています。
- 労働時間の適正管理
- 年次有給休暇の取得義務化
- 雇用形態にかかわらない公正な評価制度
パートタイム・有期雇用労働法のポイント
この法律では、不合理な待遇差の禁止と説明義務の強化が柱となっています。
雇用形態を問わず、職務内容や責任が同等であれば、以下の項目で同等の待遇を求められます。
- 基本給
- 賞与
- 各種手当(通勤手当、住宅手当など)
- 教育訓練の機会
- 福利厚生(休暇制度、施設利用など)
また、非正規雇用者が企業に対して待遇差の説明を求めた場合、企業は合理的理由を明確に提示する義務があります。
これにより、制度の透明性が高まり、従業員の納得感や信頼にもつながります。
労働者・事業主向け支援ツールとは
厚生労働省では、企業の制度導入を支援するため、以下のようなツールやサービスを提供しています。
- ガイドライン:制度運用の判断基準を明示
- Q&A資料:制度内容や対応例を解説
- 職務分析・職務評価シート:職務内容の可視化を支援
- 相談窓口(総合労働相談コーナー):各地の専門家による無料相談
- キャリアアップ助成金:制度導入・待遇改善にかかるコストの支援
・働き方改革関連法
・パートタイム・有期雇用労働法 改正ポイント
・待遇差の説明責任
・キャリアアップ助成金 支給要件
・同一労働同一賃金 Q&A・相談窓口
まとめ
同一労働同一賃金の実現に向けて必要なこと
制度の実現には、単なる法令順守にとどまらず、企業文化や人事制度そのものの見直しが求められます。
- すべての従業員の職務内容・責任範囲の明確化
- 評価基準・処遇方針のルール化と共有
- 非正規雇用者への情報開示と丁寧な説明
実践事例から学ぶ成功の秘訣
成功事例に共通しているのは、職務評価制度の導入と、待遇基準の可視化です。
特に中小企業では、以下のような取り組みが効果を上げています。
- 現場の声を制度設計に反映(ボトムアップの視点)
- 社員との対話・意見交換を通じた納得形成
- トップダウンと現場の協働による制度の根付かせ
働き方改革を通じた職場環境と社会全体の改善
同一労働同一賃金の実現は、制度対応にとどまらず、従業員の働きがい・エンゲージメント向上につながります。
- 生産性の向上と離職率の低下
- ダイバーシティ推進とインクルーシブな職場環境
- 企業の競争力強化とブランド価値向上
社会全体としても、公平性・持続可能性のある労働市場が築かれ、多様な人材が活躍できる環境の整備が進みます。
・職場環境の改善と働きがい向上
・評価制度改革とエンゲージメント
・非正規雇用と納得感のある制度設計
・ダイバーシティ経営と人的資本投資
・持続可能な人事戦略

求人・採用にまつわることなら何でもご相談ください
アド・イーグルってなんの会社?
株式会社アド・イーグルは、株式会社リクルートホールディングスのトップパートナーとして様々なメディアを取り扱っている総合広告代理店です。リクナビNEXT・タウンワークなどの求人メディアやAirワークなどの企業HPのサービスやindeedなどの求人情報検索サイトを活用して各企業の課題に合わせた採用活動を提案・支援しています。