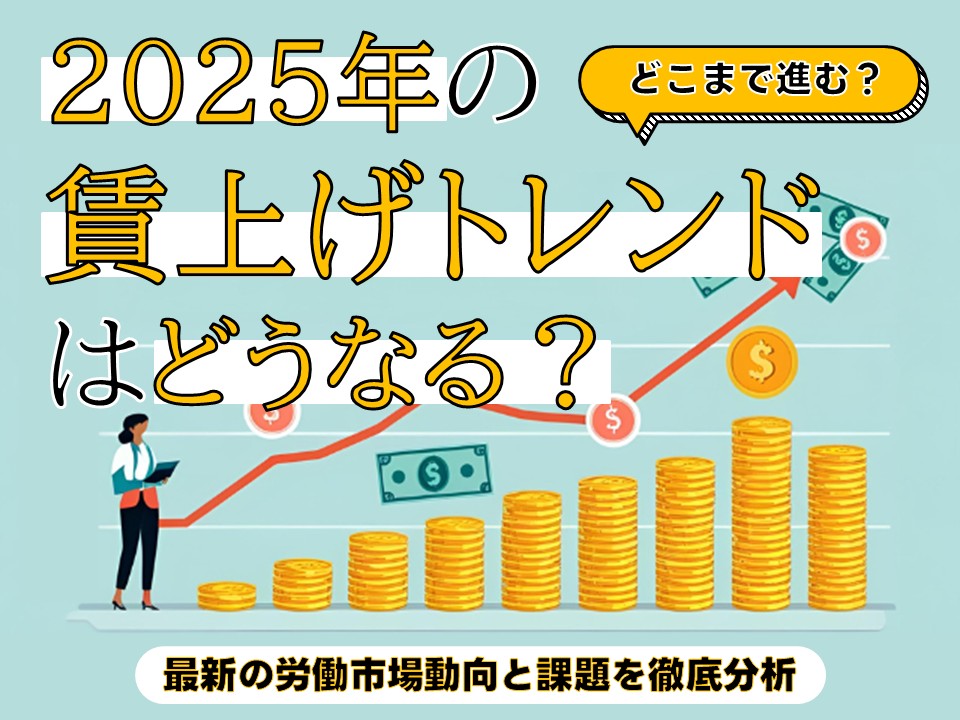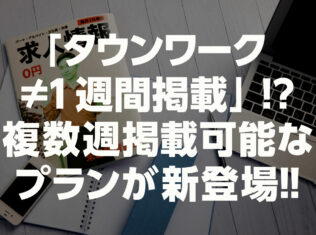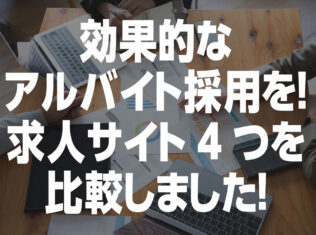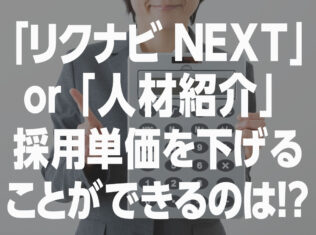日本の労働市場では、物価高騰や人手不足を背景に賃上げの動きが活発化しています。
2024年の春季労使交渉(春闘)では平均賃上げ率が33年ぶりに5%を超え、大幅な賃上げが相次ぎました。
しかし同時に物価上昇に追いつかず実質賃金はマイナスが続いており、労働者の生活改善は道半ばと言えます。
こうした状況を踏まえ、2025年に向けて労働市場はどのようなトレンドを示し、企業・個人は何に注目すべきなのでしょうか。
本記事では、最新の賃金動向や生産性向上の取り組み、経済・雇用に関するデータを基に、今後の課題と対策を考察します。
【手軽に無料で掲載できる!】Airワークの掲載方法や料金を徹底解説|よくある質問にも回答!
目次
労働市場の現状と賃上げトレンド
日本では少子高齢化による生産年齢人口の減少が進み、企業は人材確保のために賃上げせざるを得ない状況です。
慢性的な人手不足が深刻化する中、優秀な人材を惹きつけるため各社は賃金水準の引き上げに踏み切っています。
実際、2025年に賃上げを予定している企業は全体の85.2%にのぼり、前年(84.2%)からわずかに増えて最近で最も高い割合となりました。
賃上げ幅は定期昇給に加えて基本給を底上げするベースアップを含めた合計でおおむね3~4%程度が主流です。
大企業の中央値は約4.0%、中小企業では3.5%とされ、中小でも5%以上を計画する企業が4社に1社以上あります。
もっとも、連合(日本労働組合総連合会)が掲げる「全体5%以上・中小6%以上」の目標達成にはなおハードルが高いのが実情です。
大企業と中小企業における賃上げの違い
賃上げの動向を見ると、大企業と中小企業の間には依然として大きな差があります。
2024年の春闘では、サントリーなどの大手企業が平均7%前後の昇給を実現し、組合要求に満額回答するケースも見られました。
これに対し、中小企業では人件費の増加が業績を圧迫し、賃上げを実施したくても難しい状況が続いています。
一方で、中小企業でも人手不足が深刻な業界では、5%以上の賃上げを計画する企業が4社に1社以上あり、人材確保のために思い切った対応を迫られています。
特に、製造業やIT業界では即戦力の人材が不足しており、賃金を含めた待遇改善が不可欠です。
こうした状況は、賃上げが企業規模によって二極化している現状を浮き彫りにしています。
新卒採用における初任給引き上げの動向
賃金水準の見直しは新卒採用にも及び、初任給の大幅引き上げが相次いでいます。
例えば、ファーストリテイリング(ユニクロ)は2025年入社の新卒初任給を3万円増の33万円とし、年収で約1割増加させました。
また、大和ハウス工業は大卒初任給を40%増の月額35万円に引き上げると発表しています。
こうした初任給アップの背景には、深刻な人手不足下で若手人材を確保したい狙いがあります。
新卒採用での待遇改善は、単なる一時的な賃上げにとどまらず、企業の将来的な競争力を左右する重要な施策です。
企業間で賃金引き上げ競争が広がることは、労働市場全体としての賃上げトレンドを一段と押し上げる要因となっています。
賃上げが経済・雇用に与える影響
相次ぐ賃上げの波は労働者の収入を増やしていますが、その効果は物価上昇率との兼ね合いで見ていく必要があります。
近年の物価高により実質賃金はマイナス傾向が続いており、賃上げが実施されても労働者の生活水準が向上しきれていないとの指摘があります。
実際、2023年・2024年と続いた賃上げで名目賃金は上昇しましたが、物価高の影響で実質賃金はなお減少しているため、2025年も引き続き賃上げによる底上げが求められる状況です。
政府や中央銀行も、賃金と物価の動向を注視しています。
日本銀行は2024年の春闘で大幅賃上げが相次いだことを受け、長年続けてきたマイナス金利政策の解除に踏み切りました。
政府も春闘の結果を踏まえて最低賃金の大幅引き上げや中小企業向けの支援パッケージを打ち出し、賃金格差是正を後押ししています。
賃金上昇は消費を下支えする一方、企業収益や物価への影響も及ぼすため、政策当局は賃金と物価の好循
環を目指しつつインフレを抑制する難しい舵取りを迫られています。
2025年の賃上げ見通しについて、複数の調査が引き続き高い昇給率を予測しています。
第一生命経済研究所は2025年春闘で約4.8%の昇給が見込まれると予測しており、みずほリサーチ&テクノロジーズも約4.6%と高水準の継続を見込んでいます。
これにより、2025年度には消費者物価の伸び(前年比+2%前後)に対して実質賃金がわずかながらプラスに転じ、家計の購買力改善に繋がると期待されています。
長らく停滞してきた日本の賃金がようやく物価上昇を上回り、「賃金と物価の好循環」が現実味を帯びてきたと言えるでしょう。
もっとも、企業規模や雇用形態による賃金格差は依然大きく、中小企業では原材料費高騰分の価格転嫁が進まない場合に賃上げ余力が削がれてしまう懸念もあります。
実際、2024年には業績が伸びない中で離職防止のため苦渋の賃上げを行った中小企業もありました。
持続的な賃上げのためには生産性の向上や適正な価格転嫁が不可欠であり、賃上げの潮流を社会全体で途切れさせず定着させていく努力が求められます。
生産性向上に向けた最新の取り組み
賃金を持続的に引き上げるには、企業の生産性向上が不可欠です。
限られた人手でより高い付加価値を生み出すことで昇給の原資を確保し、物価上昇によるコスト増にも対応できます。
昨今、多くの企業がデジタル技術の活用や業務プロセス改革による生産効率アップに取り組んでいます。
例えば、人手不足の中で労働生産性を高める手段としてAIやロボットなど先端技術の導入が重要なポイントとなっています。
作業の自動化・省力化を進め一人当たりの生産性が向上すれば、その分だけ賃上げを行う余地も生まれると考えられます。
また、社員のスキル向上(リスキリング)も生産性向上の鍵です。
企業側では研修制度の充実や自己学習支援を通じて人材育成に力を入れる動きが強まっています。
大和ハウス工業は賃上げと並行して、社員が自主的に学べる「自律学習プラットフォーム」を導入し、従業員の能力開発を後押ししています。
社員の意欲やキャリア志向に合わせて学び直しや挑戦を促すことで将来の成長を担う人材を育成する狙いです。
さらに同社は定年年齢の引き上げ(67歳選択定年制度)を実施し、経験豊富なシニア層が長く活躍できる環境づくりも進めています。
企業はこのように若手からベテランまで人材の潜在力を最大限に引き出し、生産性向上と人的資本の有効活用に努めています。
関連:【今さら聞けない…?】リスキリングとは?|【完全ガイド】目的、方法、事例から実践まで
加えて、従業員の福利厚生制度を見直す動きも注目されます。
賃金本体の引き上げだけでなく、手当や福利厚生によって実質的な手取り収入を増やすアプローチです。エデンレッドジャパンは定期昇給を「第1の賃上げ」、ベースアップを「第2の賃上げ」と位置づけ、非課税枠のある福利厚生で従業員の可処分所得を増やす施策を「第3の賃上げ」と提唱しています。
このような福利厚生による手取りアップ策は、限られた予算でも従業員満足度を高められる手法として注目されています。
「賃上げ」は何も基本給の増額だけを意味せず、税優遇のある福利厚生や賞与増額など柔軟な手段を組み合わせることで、従業員のモチベーションと生活水準を向上させることができます。
企業が取り組むべきポイント
以上を踏まえ、企業にはいくつか重要なアクションが求められます。
POINT(1)
第一に、賃上げを将来への投資と捉えることです。
人材を会社の「資本」と位置づけ、中長期的視点で処遇改善に取り組むことで、優秀な人材の確保・定着と企業価値向上の好循環が期待できます。
なお経団連も賃上げ定着を「社会的責務」と位置づけ、企業横断での底上げを促しています。
大企業だけでなく中小企業も含めて賃上げを実現するには、下請け取引の適正化や生産性向上支援など企業間連携と公的支援の活用が欠かせません。
POINT(2)
第二に、生産性向上策の推進です。
デジタル技術の導入や業務改革、人材育成によって生産効率を上げることが、持続的な昇給の前提となります。
自社の業務フローを見直してムダを削減するとともに、従業員が新たな技術に適応できるよう研修・教育に投資し、スキル転換(スキルシフト)を支援すべきです。
政府も中小企業の設備投資・IT導入・人材育成を後押しする補助金や税制優遇策を用意しており、こうした制度も積極的に活用しながら生産性向上に努めることが重要です。
POINT(3)
第三に、柔軟な報酬制度の活用です。基本給の引き上げだけに固執せず、賞与や福利厚生を組み合わせて総合的に処遇を改善する発想が求められます。
特に中小企業では固定費となる基本給の大幅増が難しくても、成果に応じた賞与支給や従業員が実感しやすい福利厚生の充実によって報いることが可能です。
最後に、賃金格差への目配りも欠かせません。
大企業と中小企業、正社員と非正規社員との格差を放置していては、日本全体の底上げは進みません。
大企業は取引先中小企業への配慮を強め、中小企業は政府支援も活用しつつ賃上げと事業効率化に取り組む必要があります。
産業全体で底上げが進めば、消費拡大によって自社の市場も拡大し、巡り巡って企業利益にもプラスとなるでしょう。
個人が取り組むべきポイント
労働者個人も、賃上げの潮流と物価動向を踏まえた対応が求められます。まずは自身のキャリア形成においてスキルアップを継続することが重要です。企業が求めるスキルはデジタル技術の進歩とともに変化しています。AI時代に対応できるITスキルや高度専門知識を磨くことは、自分の市場価値を高め、賃金交渉でも有利になるでしょう。特に、プログラミングやデータ分析、AIの基礎知識といったスキルは、今後ますます需要が高まると予想されています。
また、労働市場が活況な今、転職や社内異動のチャンスを逃さず、より良い待遇や成長機会を追求する姿勢も大切です。職務経歴書をアップデートし、転職エージェントや企業の採用ページを定期的にチェックしておくと、いざというときにスムーズに行動できます。自らの努力と交渉によってキャリアアップを図り、賃上げの恩恵を最大限に引き出しましょう。
スキルアップとリスキリングの重要性
スキルアップに加えて、**リスキリング(新たなスキルの習得)**も今後のキャリア形成に欠かせません。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、既存の業務スキルだけでなく、新しいテクノロジーに対応できるスキルを習得することが求められています。例えば、プログラミング、データサイエンス、クラウド技術、サイバーセキュリティなど、これまで専門職の領域だったスキルが一般職でも必須となりつつあります。
企業側もリスキリング支援を強化しており、eラーニングや外部研修の費用補助、勤務時間内の研修受講などを行っています。こうした制度を積極的に利用し、計画的に新しいスキルを身につけることが賃上げや昇進に直結します。リスキリングは一朝一夕で効果が出るものではないため、少しずつ継続的に学ぶ姿勢が重要です。
収入増と支出のバランス管理
一方で、収入が増えた場合でも家計管理をおろそかにしないことが肝要です。賃上げによって手取り収入が増えても、同時に物価上昇で支出も増えている可能性があります。例えば、食料品や光熱費、交通費など日常的な支出はインフレの影響を受けやすく、収入増加分が実感できないケースもあります。
臨時収入やベースアップ分に浮かれて消費を拡大しすぎず、将来に備え貯蓄・投資に回すなど計画的に活用することが賢明です。三菱UFJ銀行のMoney Canvas(マネーキャンバス)も「賃上げ傾向が続く中で、増えた収入をどう活用するか、家計管理や投資戦略をしっかり練っておくことが重要」と指摘しています。
例えば、増えた分の20%は緊急資金、30%は積立投資、残りは生活費や娯楽費に充てるといったルールを設けると、無駄遣いを防げます。収入増と支出増のバランスを見極め、インフレに負けない資産形成を心がけることが、実質賃金を守ることにも繋がるでしょう。
労働条件の見直しと自己防衛策
さらに、自身の労働条件や権利に対する意識を高めることも必要です。例えば、残業代の未払い、契約違反などに気づかず働いていると、賃上げ分が帳消しになりかねません。労働基準法や労働契約法に基づき、労働時間や賃金、休暇についての権利を理解しておくと、トラブルを未然に防げます。
また、労働組合の交渉で賃上げが実現するケースも多く、自身の職場や業界で声を上げることも大切です。
組合がない場合でも、同僚と協力して労働環境の改善を訴えることで、会社に変革を促すことができます。
もし現在の待遇が不当だと感じる場合には、転職や専門機関への相談など適切な評価を得るための行動も検討すべきでしょう。
特に、転職活動を進める際には、転職エージェントや転職サイトの活用が効果的です。業界ごとの賃金相場や条件交渉のコツを教えてくれるため、現職との比較材料にもなります。
自己投資のすすめ: 健康とスキルの両立
賃上げ分をどのように使うかは、将来の生活に大きく影響します。自己投資としてスキルアップに使うのはもちろん、健康管理も重要な投資です。 賃金が上がっても、健康を損なっては本末転倒です。例えば、健康診断やスポーツジム、健康食品などへの支出は、長期的に見れば医療費の抑制や労働意欲の向上に繋がります。
また、自己啓発のための書籍購入や資格取得講座への投資も、将来的な昇進や賃上げのきっかけになります。資格手当がある会社なら、取得した資格が直接的に給与に反映されることもあるでしょう。自己投資をバランスよく行うことで、賃上げ分を効率的に使い、長期的な収入増を目指すことが可能です。
まとめ
日本の労働市場は、歴史的な賃上げ局面と構造的な人手不足という大きな転換点に差し掛かっています。
賃金上昇は労働者の生活向上と経済活性化に不可欠ですが、それを持続可能にするには生産性向上と企業努力が伴わなくてはなりません。
個人も自己研鑽と賢明な資産管理によって、この追い風を確かなものにできます。
企業と個人がそれぞれの立場で適切な対応策を講じ、賃金と物価の好循環を定着させることができれば、日本経済全体の底上げへと繋がっていくでしょう。
賃上げのトレンドを正しく理解し、先手を打って行動することが、これからの時代を生き抜く上での鍵となります。
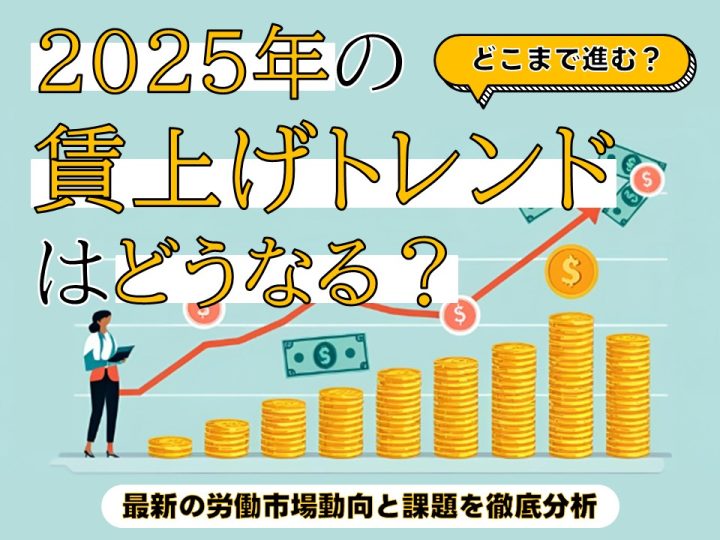
求人・採用にまつわることなら何でもご相談ください
アド・イーグルってなんの会社?
株式会社アド・イーグルは、株式会社リクルートホールディングスのトップパートナーとして様々なメディアを取り扱っている総合広告代理店です。リクナビNEXT・タウンワークなどの求人メディアやAirワークなどの企業HPのサービスやindeedなどの求人情報検索サイトを活用して各企業の課題に合わせた採用活動を提案・支援しています。